高崎アーカイブNo.14 たかさきの街をつくってきた企業
新町紡績所(1877年〜1975年)
日本の産業近代化の原点
建築も経営も外国人に頼らない官営の模範工場として設立
日本人の手で初めて建築した紡績所
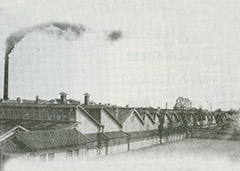 明治40年代に増設された木造のこぎり屋根工場
明治40年代に増設された木造のこぎり屋根工場 赤レンガ倉庫
赤レンガ倉庫
明治政府の殖産興業政策の一環で、明治10年(1877)に新町に建設された「内務省勧業寮屑糸紡績所」は、日本の近代化を進めるうえで大きな役割を果たしました。
また、工場の建設はウィーン万博で日本館建設に棟梁として携わり、西欧建築を身につけて帰国した山添喜三郎が、設計から施工までを担当しました。
明治5年(1872)に設立された官営富岡製糸工場が、フランス人のポール・ブリューナーを首長とし、設計から工場経営にまで携わったことに対し、新町紡績所は日本人の手によって造られ、近代的なヨーロッパの技術を日本に普及させる橋渡しの役割を果たしました。
現在、その建物はクラシエフーズ㈱(旧カネボウフーズ)の所有となり、木造煉瓦造の旧製品倉庫など当時の姿を今にとどめています。
輸出品の生産拠点として期待される
屑糸紡績というのは、当時廃物と見なされていた屑糸や屑繭・出殻繭を利用して生糸を生産するものです。
当時産業が未発達の日本は、産業革命を経験したヨーロッパ諸国と貿易を始めましたが、輸出すべき商品がないために輸入超過に悩んでいました。そこへ廃棄物と思われていた屑糸から生糸が生産できるとあって、明治政府はこの新町屑糸紡績所に大きな期待をかけ、内務卿の大久保利通以下、大隈重信、松方正義、伊藤博文等政府の高官を迎え、華々しく開業式が行われました。
紡績所の生みの親、佐々木長淳
屑糸紡績所の設立を政府に提案し、紡績の建設地を新町に選定し、工場設立の責任者となったのは、初代所長の佐々木長淳です。
佐々木は元福井藩士で廃藩置県後に新政府の工部省に出仕し、以降勧業事業を中心に従事しました。明治6年(1873)のウィーン万国博覧会の担当者として、万国博覧会に出席し、あわせてイタリア・フランスの養蚕・製糸・紡績業の視察を行いました。
帰国した佐々木は政府から工場設置場所として武蔵、甲斐、相模、上野の四カ国に派遣され、上野国緑野郡新町駅を最適地として推しました。
上州は養蚕で有名な土地であり、屑糸・屑繭の購入に便利なうえ、新町は温井川が流れ水利に恵まれていました。また利根川・烏川の舟運の便があり、東京から比較的近いという点も有利でした。新町屑糸紡績所は全国の模範工場として、紡績器機の研究が第一の目的とされました。
ここに勤めたと言えば縁談もうまくいった
創業当時、女工手(男工手は技男、女工手は技女と称されました)は士族の娘でなければ採用されなかったので、主に高崎、前橋藩士の娘が多く、寄宿舎に帰っても上品で、新町紡績所に勤めたと言えば、縁談もまとまったといいます。
女工手の服装は、看護師に似たもので、主席工、工頭が紺色で平工はすべて浅黄色の木綿を着ていました。
給与は女工手が一日8〜22銭までで11銭前後が比較的多く、男子は1日20〜48銭位で22銭位が平均とされ、一般からうらやましがられたといいます。食事は昼食の箱弁当が一銭で食べきれないほどだったと伝わります。総人員は280人程でした。
官営から民営に
明治20年(1887)頃に新町紡績所で生産された絹紡糸は、京都以西の地域、東京、桐生を主体に使用されていましたが、中でも精紡糸の八割以上は西京に販売され、さらに丹後に送られて縮緬の緯糸として使用され、ここに「紡績縮緬」の誕生をみました。なお、各地で試織した結果、絹織物とは見えず、綿布よりは良いといった程度の出来だったので、好んで使用されるまでには至らなかったようです。
明治20年(1887)までの約10年間、農商務省勧農局屑糸紡績所(明治15年に新町紡績所と改称)として官営でしたが、創設の意図が民業の振興にあったことから、これを民間に移すことになり、紡績所は三井家に約15万円で払い下げられ、明治20年6月、三越得右衛門名義で経営されました。
三越呉服店の経営に移り、「新町三越紡績所」(後に三井紡績所)と改称、同時に輪具式紡績機1,200錘を増設しました。
鐘淵紡績に合併され、新たなスタート
明治35年(1902)三月、京都で全国絹糸紡績総合会が開かれ、絹紡六社が合同することになりました。この結果、「絹糸紡績会社」が創立され、「絹糸紡績株式会社新町工場」と改称されました。
明治37年(1904)の日露戦争に大勝した結果、産業界はようやく活況を呈し、休錘に休錘を重ねた紡績業界も市況の活況によって在庫品を売りつくし全錘運転をするようになりました。特に紬糸の売れ行きは好調で、工場は昼夜を問わず操業を延長し、初めて株主に対し一割の配当をすることができました。
しかし、業界は再び不況に見舞われ、明治44年(1911)3月、絹糸紡績株式会社は鐘淵紡績会社に合併され、「鐘淵紡績会社新町支店工場」として新たなスタートを切りました。
その後、最盛期には3,000人以上が働く一大工場となりましたが、繊維産業の退潮期を迎え、昭和50年(1975)に絹糸紡績は操業停止となり、由緒深い新町工場は歴史の幕を閉じました。
※参考資料『鐘紡新町工場九十年史』
