高崎アーカイブNo.17 たかさきの街をつくってきた企業
高盛座(1894〜1929)
藤守座(1880〜1916)
明治から大正期
高崎市民の娯楽の殿堂として輝いた二つの劇場
伝馬役の費用を補おうと新町(現あら町)で始まった興行
江戸時代、高崎藩は尚武の気風が強く、文武を奨励し、領内住民に歌舞音曲、手踊りの類を許しませんでした。当時、中山道の宿場町として大名行列その他の際に、輸送を担当する伝馬役を本町、田町、新町で負担をしていました。本町と田町は大商店が多く、人馬継ぎ立てなどの費用負担に堪えられましたが、新町は財政上の力が弱く、年々町は疲弊していきました。幕末の文久2年(1862)、新町の町民総代たちは伝馬役の費用を芝居や相撲などの興行収入で補おうと、禁制を破って藩当局に訴えました。このため総代たちは入牢、罰金などの処罰を受けました(伝馬事件)が、慶応2年(1866)になって藩当局も理解を示し、江戸大相撲の興行が許可され、相当の利益を上げることができました。
その後間もなく明治維新となり、諸制度も変革されたので、新町では常設芝居などの興行を藩当局に請願しました。
明治2年(1869)1月7日、正式に許可され、2月末から3月にかけて江戸歌舞伎役者を招き、仮設舞台で芝居興行を行ないました。そして6月には、坂東彦三郎等によって「坂東座」が新町に創建されました。落成した月には尾上菊五郎や阪東美津五郎などの歌舞伎役者を招いて興行した記録が残っています。
■高盛座
歌舞伎座を模した県下一の劇場
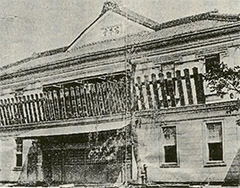 明治40年に新築された八島町の高盛座
明治40年に新築された八島町の高盛座
「坂東座」は明治5年(1872)4月に火災で焼失しましたが、8月に岩井半四郎、中村仲蔵等によって同じ場所に再建され、「岩井座」と改称し、芝居興行を続けました。
日本鉄道会社中山道線が竣成し高崎停車場の位置が決まると、岩井座のところが停車場入口の道路となっていたため、明治17年(1884)3月に八島町北側(井上山種ビルの辺り)に移転し、小屋掛けで興行しました。
その後、明治27年(1894)12月2日の改築を機に、「高盛座」と改称。株式会社組織の貸し劇場となり、頭取兼取締役は久保村徳次郎、副頭取兼取締役は後に白衣観音を建立した井上保三郎でした。
建築は、東京木挽町(中央区銀座)の歌舞伎座を模し、市内で初めて無数の花電灯を取り付けるなど、名実ともに県下一の劇場となりました。以降、市内のほとんどの興行はここで行われました。
初の活動写真を上映
明治30年(1897)に東京と大阪などで「活動写真(映画)」が初公開され、高崎では明治32年11月の8日間、高盛座で上映されたのが初めてでした。内容は東京をはじめ各地の芸者の踊り、欧米や日本の風景を写した短いもので、日替わりで内容を差し替え、円熟した弁士が説明にあたりました。動く写真を見た観客は大喜びで、連日満員でした。
昭和4年(1929)に取り壊されるまでの35年間、高盛座は娯楽の殿堂として高崎市民に親しまれました。
全盛期は大正時代で、菊池寛や久米正雄らを招いての文芸講演会、沢田正二郎率いる新国劇「国定忠治」の公演なども行われました。中でも特筆すべきは,明治歌舞伎界の立役者であり、不出征の名優といわれた九代目市川団十郎と並び称された、五代目尾上菊五郎の来演でした。一座を迎えるため、市内の有志が一口20円の株を引き受け、資金に当てたといわれています。(今の金額に換算すると15万円くらい)菊五郎一座の公演期間中は、連日超満員という盛況ぶりでした。
しかしその後、映画の流行から昭和四年に廃業になりました。
■藤守座
後に映画上映館として映画の灯を守り続けた
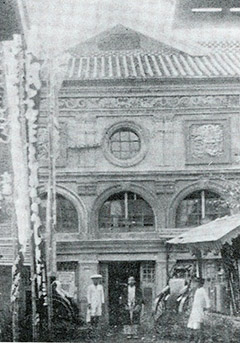 新紺屋町の藤守座
新紺屋町の藤守座
藤守喜太郎が明治10年頃に田町通りで「田琴(毎)座」という寄席を経営し、評判がよく大入りが続きました。その後、明治13年(1880)1月の大火で焼失したため、新紺屋町(元のオリオン座の場所)に新築移転し、同年5月に舞台開きを行いました。『高崎繁昌記』が刊行された明治30年ごろには、高盛座と並んで高崎町民の娯楽の場として賑わいをみせました。
創業者の藤守喜太郎は、東京で人力車が発明されるとすぐに高崎で取り入れ、人力車事業を始めたり、君が代橋をかけて橋銭を稼いだりと、興行的な才能のあるアイデアマンでした。
藤守座は、大正5年(1916)に芥川振次郎、藤井勘一郎らによって「㈱世界館」となり、活動写真上映館として再スタートしました。さらに、前橋の映画興行王、野中倉吉の手に移り改築されて「第二大和」となりました。
その後も「高崎松竹映画劇場」、「オリオン座」と名を変えて、昭和37年(1962)に鉄筋コンクリート2階建てに改築、1階に食堂、2階に映画館という新方式で映画の灯を守り続けました。
寄席や演芸なども盛んで賑わった席亭
「高盛座」と「藤守座」の二つの劇場のほかに、「席亭(寄席・演芸場)」として、新町の「高崎亭」、鞘町の「共楽館」、新紺屋町の「松田亭」の三軒が、『群馬県営業便覧』(明治37年発行)に掲載されています。また、高崎の寄席状況について明治10年12月の『郵便報知新聞』によれば、「芝居は田町の藤守座、新町の岩井座等にて皆櫓を上げたり、寄席は七軒紺屋町にハ軽業を興行せり」とあって、寄席の盛んな様子を伝えています。
なかでも明治31年設立の松田亭では、義太夫、浪花節、講談などが行われ、後に「睦花亭」と改称。市内唯一の寄席として営業を続け、昭和初期に閉館しました。
※参考資料「高崎市史 通史編4」、「高崎繁昌記」等
※写真資料 「高崎市史 通史編4」(明治40年二新築された八島町の高盛座)、「高崎市史資料編9」藤守座(豊嶋とみ枝氏所蔵)
