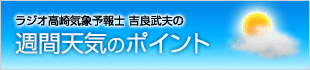ちょんまげ時代の高崎
第十三話 間部詮房って誰?

高崎城主大河内家の間に間部詮房(まなべあきふさ)という殿様が挟まっている。五代将軍綱吉が亡くなり家宣が六代に就任すると、輝貞公は越後の村上に左遷され高崎五万石の城主となったのが詮房。この方は、六代家宣、七代家継の補佐役として活躍したが、両将軍とも在位四年で亡くなったため高崎城主は八年間であった。
詮房の父清貞は能役者の喜多六大夫の衣装係だったことから、詮房も喜多に弟子入りしたと言われる。しかし、「間部家文書」(高崎市刊)には少年時代の記録はなく本当のところは分からない。十九歳のとき甲府宰相綱豊(後の家宣)の小姓となってから驚異的な栄進が始まる。綱豊が能楽を愛好したうえ間部の才覚を買ったこともあり次々と引き上げられ、家宣が綱吉の後継者となると一万石の大名となり、従四位下・侍従という大抜擢を受けた。
これだけでも大出世だが、家宣が将軍に就くと老中格となり、大名とはいえ無城主であったが、井伊さんをはじめ代々譜代で老中の家格が城主であった高崎を望んで与えられたという極めて異例な出世を成し遂げた。
高崎城主になったが、詮房自身は高崎には来られなかった。と言うのは、家宣の時は新しい幕閣創りのため、また、家継は幼少であったため、江戸を離れることがままならなかった。特に、病に倒れた家宣が、理論面での推進役で儒学者新井白石の進言を受け入れ、幼少の鍋松(後の家継)を後継として詮房に後事を託してからは難しかった。
四歳の将軍は詮房に抱かれて表御殿に出るほどで、詮房が外出先から戻ると「越前(詮房は越前守)帰ったか」と出迎え、抱かれて奥に入ったと言われる。そんな状況から老中などの宿直制が敷かれ、家宣にとって父のような存在であった詮房は、昼夜近侍して帰宅することはなかった。高崎へ来られないのも道理である。