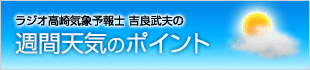ちょんまげ時代の高崎
第十六話 大河内氏の祖は源

ちょんまげ時代は源氏の末裔を称する家が多い。平清盛が公家の僕からの脱皮をはかり、源頼朝が武家の天下を創設したからであろう。松平氏である家康が徳川を名乗ったのも、名門源氏を強調したかったからである。
三河周辺で松平と勢力争いをしていた守護衆の今川や吉良などは、足利源氏の出身であった。これに対抗するため、家康は源義家の孫新田義重の末子で尾島町徳川(得川)に居た義季を祖とする流れを汲む系図詐称をしたと言われる。また、武家政治の世界に信じられていた源平交代思想から、平氏の織田信長の次ぎに天下を取るには源氏である必要があったとも言われる。
同じ源氏を称するのでも、輝貞公の源朝臣(みなもとのあそん)は松平になったからではなく、遠祖を源頼政卿としているので、「我が家は源の流れですよ」と世間に示すために名乗ったものである。武家は自分の家系を誇示したいため、「源平藤橘」のいずれかを名乗った。つまり、源氏か平氏、あるいは藤原氏か橘氏のいずれかの流れを汲んでいると世に示した。橘氏は勢力が広がらなかったが、藤原氏は平安時代から江戸時代に至るまで、貴族社会の中枢で栄え、高崎の殿様となった安藤氏や薩摩の島津氏も藤原姓を称した。
源氏というと、源頼朝を輩出した清和天皇の流れを汲む清和源氏が有名だが、この他にも、宇多源氏や村上源氏など十七もの天皇家から臣籍に入って「源」を賜った系統がある。平安時代になると皇室経済にひっ迫から、増加した皇子・皇孫の整理をはかり、冗費を省く必要から始まった。この宮家を創らないで特別の姓を与えた制度を「賜姓皇族」といい「朝臣」は皇子皇孫の尊称である。大河内家の源朝臣は清和源氏の本流である源頼光四世頼政卿の末裔を表している。