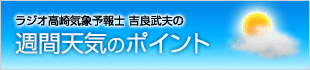ちょんまげ時代の高崎
第十八話 幕閣で活躍輝高公

輝貞公は五十歳のとき輝規(てるちか)公を養子に迎えたが、八十歳で隠居されるまで幕閣として活躍していたので、輝規公は三年数カ月の在位で子息の輝高公が高崎三代目となった。どの世界も三代目は難しいが、輝高公が高崎大河内を盤石なものとされた。
十二歳のとき将軍吉宗に拝謁し、二十五歳で家督七万二千石を継ぎ奏者番に。二十七歳で大坂城代、三十一歳で京都所司代、三十六歳で老中へとエリート階段を上り、九代家重、十代家治両将軍の時代約二十年間に亘って老中を務められた。多年の激務に対する褒賞として、一万石加増され以降の高崎は八万二千石が続く。
官位も、大坂城代のとき従四位下右京大夫となり、京都所司代のとき侍従に任ぜられた。これらの官位は律令制時代からのものだが、幕府が殿様たちに簡単に領地やお金を与えられないため、名誉を与えてくすぐる方法として朝廷よりいただく形を執っていた。大河内家は五代までが従四位下、六代以降は若くして亡くなられたりしたため従五位下。従って、官位相当からして、四位の方は右京大夫、五位の方は右京亮に叙せられた。官名の右京は京都洛中の右部分を専門に担当する役所のことで大河内家遠祖源頼政卿が右京大夫に叙せられたことに因む。
輝高公は、幕閣として次世代に我が国を揺るがすことに繋がる事件を処理された。一つは宝暦事件(この事件は竹内式部事件とも呼ばれる)で、現状に不満を持つ公家が、皇政復古を唱え煽動したことに対し明快に裁決されたと『旧高崎藩概誌』に記録されている。もう一つは、西上州に起こった絹一揆で城下でも打ち壊しが起こり、初めて鉄砲を持って制圧するという事件である。前者は結果として朝廷と幕府の対立を深め、後者は約百年後の幕府崩壊の底辺となる難事件の解決であった。