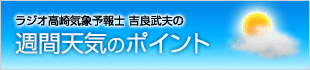ちょんまげ時代の高崎
第二十話 譜代老中格高崎城主

江戸時代は、中央の幕府と地方の藩による幕藩体制時代と言われるが、藩という言葉は明治新政府によって作られたものである。明治元年に旧大名領を藩という公称で取り敢えず存続させたが、同四年に廃藩置県を断行したので藩は県となり、公式には使用しなくなったため、四年しか用いられなかった。しかし、大名の家名で呼ぶより地名から付けられた藩名のほうが分かり易かったのか、大名領やその城下町を藩と呼ぶのが一般的になって、今日に至っている。
大名が家門(親藩)、譜代、外様と区分されるのは良く知られているが、他には国持(国主)、国持並(準国主)、城主、城主格、無城の分け方がある。国持は、加賀国他を有していた前田家や、薩摩国の島津家のように、領国が一国以上にわたるもので二十家、国持並は国持に準じるもので三家を数える。国持と国持並は、柳沢家と福井及び松江の松平家を除くと全て外様大名である。
そもそも家門と譜代は徳川一族であり、国持大名の領地以外の国は殆ど徳川家のものであるから、高崎のように譜代大名は徳川家領地の一部をあてがわれたに過ぎない。その中で、城を持てない大名(上州では小幡や七日市)が百二十余もあったが、高崎は城持だから「譜代の城主」に分類される。従って、輝貞公の廟の中に建っている碑文でも藩主でなく城主と彫られている。
関八州(関東地方)は江戸の周辺であるため殆ど譜代の領地であり、その中でも高崎は、川越、佐倉、古河などとともに老中が配される要衝の地であった。高崎初代城主の井伊直政公の時代は老中の制度がなかったが、徳川政権の筆頭として大老的立場であった。その後、高崎城主となった代々の殿様の中から、安藤重長、間部詮房、そして大河内家の輝貞公、輝高公、輝延公の合計五人の方が老中に就任している。