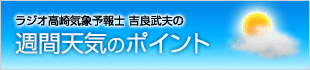たかさき町知るべ
柳川町(やながわちょう)

旧高崎城の北側堀外にある町で、北は嘉多町、西は堰城町、常磐町、南は高松町、東は新紺屋町と寄合町になっている。
この町は東部と西部とに分けられていて、西部は江戸時代には城内の「北郭(きたくるわ)」と呼ばれ、武家の屋敷があった。地内中央を走る南北の路の東側は、明治初年まで芦や雑草の生い茂る湿地帯で、白昼に狐や狸が出るさびしいところであり、また、この湿地帯は、城の防備の一部分にもなっていた。
新紺屋町へ通じるあたりには藩の厩舎があった。松山病院近くには藩校の「文武館」があり、火災に逢って廃館になった後は、その跡地に代官の屋敷ができた。その後、この代官屋敷もまた、文化九年(一八一二)一〇月、本町からおこった大火によって類焼し、代官屋敷は現在の宮元町の方に移り、屋敷跡地は火除け地になった。
明治維新後、城内三ノ丸に屋敷を与えられていた藩士たちは、町の西部に移された。明治期に活躍した自由民権運動の宮部襄、キリスト教の内村鑑三、日銀総裁になった深井英五らはこの町の出身である。
明治六年(一八七三)町として名がつけられることとなり、地内を流れる用水の岸に柳の大木があったことから、「柳川町」となった。
江戸時代、城の東北隅と、覚法寺南西の石橋のところに番所、玉田寺西裏に木戸があったが、廃藩によって取り払われた。町内西部の武家屋敷に対し、東部の空き地であったところは、明治以後、軍都、県都高崎の花町となり、戦後は夜の飲食街になっている。
明治三九年(一九〇六)には、柳川町一番地に佐藤裁縫女学校(現佐藤学園、高崎商科短大、附属高校、附属幼稚園の前身)が開校した。また、大正二年(一九一三)には、映画劇場の「電気館」ができた。