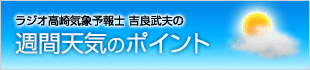たかさき町知るべ
宮元町(みやもとちょう)

高崎旧城の堀に沿って、東から南にかけての南北に細長い町である。北は中紺屋町、西は旧城内の高松町、南は若松町、東は北から鞘町、桧物町、鍛冶町、下横町となっている。
江戸時代、この町のあたりは、藩に仕えていた武士が集中して住んでいた。その中には米見役人や代官もいて、「米見町」、「代官町」と呼ばれるごく限られた範囲のところもあった。また、明治維新後に江戸藩邸から引き揚げてきた藩士とその家族が居住した、公園東側の「南郭(みなみくるわ)」もあり、これらを一つにまとめて明治四年(一八七一)に町として成立した。
「宮元町」の名は、町の南端に鎮座している頼政神社のおひざもとの意味でつけられたものである。頼政神社の祭神は、夜毎皇居に現われて帝(みかど)を悩ませた怪鳥の鵺(ぬえ)を退治したという源三位頼政(よりまさ)である。享保二年(一七一七)城主間部詮房(まなべあきふさ)に代って、越後国(新潟県)村上から、再び高崎に封じられた大河内輝貞が氏神として創建したものである。大河内氏は、松平姓であり、松平は源氏であるとしたからである。
この神社の境内には、内村鑑三の「上州人」詩碑が建てられている。
明治初年まであった石上寺跡地の宮元町一番地に、明治一〇年(一八七七)高崎宿内の小学校を統合して「高崎学校」が開校した。また、この小学校に隣接して二一年(一八八八)「高崎幼稚園」が開設されている。高崎学校は市立中央小学校の前身で、常磐町へ移転後の跡地には、大正一三年(一九二四)市立実践女学校が誕生した。この女学校は後、市立女学校、女子高校、高経大附属高校と変って現在に至っている。いま、石上寺跡地は東京電力高崎営業所となっている。
これとは別に、明治四一年(一九〇八)には県立高崎商業高校の前身である、市立甲種商業学校が、四五番地に開校した。この学校の運動場は、旧城大手前門の広場であったという。その後台町へ移転したが、その跡地には高崎幼稚園が引っ越してきた。
江戸時代、城の南、烏川の崖際には、藩主大河内家の祈願所であった真言宗の華王山大染寺という寺があった。この寺は、明治七年(一八七四)武蔵国(埼玉県)熊谷の養平寺へ移り廃寺となった。この跡地を中心にして、初代市長が切望していた「高崎公園」が明治四三年(一九一〇)に開園した。また、これよりも早く、明治一五年(一八八二)には高崎では最初の、日本キリスト教団高崎教会ができている。