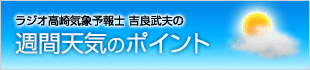高崎アーカイブNo.7 たかさきの街をつくってきた企業
高崎信用組合と上州銀行(大正8年〜現在)
大正から昭和へ、高崎の銀行合同の中心的存在
初の地元資本の貯蓄銀行「上毛貯蔵銀行」の設立
明治時代後期は、産業・経済の発展による資本需要を賄うため多くの金融機関が設立されました。養蚕業・製糸業への金融を主体としていたので、これらの産業の盛衰に左右されました。
第一次世界大戦が始まった翌年の大正4年(1915)9月、「上毛貯蔵銀行」が本店を九蔵町において設立されました。貯蔵銀行というのは、貯蓄銀行条例に基づく貯金業務を主にした銀行でした。設立発起人は、地元資本の貯蔵銀行を切望した地元の有力者、小沢宗平・井上保三郎・蝋山政次郎ら十数人。本町・田町・あら町・旭町・大橋町に支店が置かれ一斉に開業しました。
高崎の銀行合同の中心となった上州銀行の誕生
 田町に新築された上州銀行本店(大正11年)
田町に新築された上州銀行本店(大正11年)
産業・経済の発展と景気変動に対応するため、金融の強化は政府の基本方針であり、銀行の合同はその延長線上にありました。高崎を中心とする上州銀行の誕生は、前橋を中心とする群馬銀行(第一次)の誕生とともに、大正期の群馬県における銀行合同の中心でした。
上州銀行は、大正8年(1919)7月5日に設立され、頭取に小沢宗平、取締役に桜井伊兵衛・大島戸一・小林弥七等が選任されました。
当時地元には小資本の高崎積善銀行・高崎銀行・上毛貯蔵銀行の三銀行があり、まずは大資本の強力な新銀行「上州銀行」をつくり、その新銀行に三銀行を吸収合併して、実質的な大銀行を設立しようという趣旨がありました。合併により新資本金は300万円。これまでにない大銀行が誕生しました。
戦後恐慌をくぐり抜け力をつけた上州銀行
大正九年、大戦後の投機的思惑に支えられた「戦後ブーム」の反動として、株式の大暴落による「戦後恐慌」が起こりました。上州銀行や七十四銀行なども取り付け騒ぎが起こり、臨時休業を余儀なくされたことから、市の公金事務が滞ったり、会社・商店などの勤労者に賃金が支払えなくなったりする心配が生じました。市や県でも事態の収拾に乗り出し、大蔵省や日本銀行に働きかけ、日本銀行から上州銀行に150万円の救済融資をするなど、市域の金融不安を鎮めました。上州銀行の業務が健全に行なわれていたことに加え、高崎市出身の深井英五が日銀の理事であったことも、特別の便宜が図られた理由でした。
一方、七十四銀行は破綻し、代わって上州銀行が公金の取扱者になりました。その後、政府の大規模銀行創出策のひとつとして、上州銀行は藤岡銀行、安中銀行を合併していきました。
"庶民金融"高崎信用組合の誕生
 昭和2年12月、田町に竣工した高崎信用組合本店
昭和2年12月、田町に竣工した高崎信用組合本店
第一次世界大戦が始まった大正3年(1914)の六月に高崎信用組合が、産業組合法に基づく組織として設立されました。市内の有力者でつくった「同気茶話会」の人たちが発起人になり、設立運動が起こったのが始まりでした。その基盤になったのは、二宮尊徳の報徳思想を実践し、地域社会の再建・強化を目指す運動であり、至誠・勤勉と相互扶助の精神が根底にありました。高崎信用組合は、不景気を克服し金融を円滑にするため、市民の有志によってつくられたのでした。
組合員が貸付を希望したときは、理事が信用程度と貸付金の額と貸付方法を定めました。貸付を受ける場合は、保証人を立てるか、担保を入れるか、どちらかにしなければなりませんでした。貸付金額がこれまでの貸付金を合計して、出資金以内ならばその必要はなく、信用で貸してくれました。返済期間は通常一年でしたが、特別の場合は三年まで延ばすことができました。また、土地や建物、機械器具の購入、設備費や改修費などに使う場合は、10年以内の月賦または年賦返済ができました。
期待が集まり、経営が軌道にのった高崎信用組合
高崎信用組合が組織され一カ月ほどたった大正3年7月、第一次世界大戦が勃発。高崎の産業経済界は一時混乱して前途を悲観する者が多かったものの、高崎信用組合が翌年四月に新規加入を募集すると、600口が集まり、一年ほどの間に20数万円の貯金が集まりました。
大正4年(1915)当時、高崎で預貯金業務を行なっている銀行や会社は10社余りありましたが、3年据え置きの貯金が満期を過ぎても支払ってもらえなかったり、集めた資金が東京・横浜方面に流出することが多かったことに対する反動が、高崎信用組合の盛況につながりました。
戦後恐慌は、高崎信用組合の経営を大きく揺るがしましたが、模範組合として知られた高崎信用組合が、信用を失墜してしまわないように、群馬県産業主事の反町熊蔵が早く対処するよう指導しました。さらに昭和2年に始まった金融恐慌で多くの銀行が休業に追い込まれた中、高崎信用組合は休業することなく、市民のために営業を続けました。このことは組合の評価を高めることになり、昭和10年代に入ると貯金が伸びていきました。
高陽信用組合、積善信用組合を合併し、昭和26年には信用金庫法により「高崎信用金庫」に組織変更しました。そして平成26年には、高崎信用金庫は創立百周年を迎えます。
上州銀行・群馬銀行の合併、そして群馬大同銀行の設立へ
昭和7年(1932)7月7日、上毛新聞が「地方金融統制に県が母体となり、諸銀行を吸収合併して強力なる機関出現を要望」という見出しを掲げてスクープしました。県は、昭和恐慌から抜け出すためには金融統制が必要であるとし、県の援助で新銀行を設立し、そこに上州銀行と群馬銀行の二行を吸収合併して新金融機関を設立する方向で動きました。
上州銀行の地盤である高崎市を中心に強い反対運動が起こり、3回の株主総会が開かれ紛糾を重ねた結果、ようやく合併が認められました。
昭和7年9月、群馬県金融株式会社と群馬銀行・上州銀行合併の仮契約書の調印が行われました。群馬県金融㈱は、群馬大同銀行と改称され、11月には営業開始、本店は前橋市本町に移転しました。
以降、日中戦争・アジア太平洋戦争と戦争が続く中、統制経済は強化され、政府の指導する一県一行(一つの県に本店を持つ一つの銀行)主義のために銀行の合併が進められました。群馬大同銀行は昭和30年に㈱群馬銀行と改称されました。
※参考資料 『高崎市史』通史編4