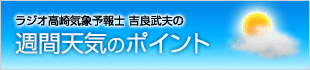高崎アーカイブNo.9 たかさきの街をつくってきた企業
音楽茶房 あすなろ/コーヒー・カレー専門店 高崎レストハウス(1957〜1982)
高崎の知性が集い、時代の新しい息吹を生んだ二つの文化サロン
音楽茶房 あすなろ
群響がきっかけで誕生。共に歩んだ音楽の館
 本町にあった頃のあすなろ
本町にあった頃のあすなろ
いまから30年前、静かに幕を閉じた音楽茶房「あすなろ」。天井の高い格調ある店内にはコーヒーの香りとクラシック音楽が流れ、壁面には県内在住の画家たちの絵が掛けられていました。またステージでは毎週のようにクラシック音楽のコンサートや詩の朗読会が開催されました。
「あすなろ」は後に詩の芥川賞といわれる『H氏賞』を受賞した詩人、崔華國(日本名・志賀郁夫)さんが、群響をモデルにした映画「ここに泉あり」を観て感動したのがきっかけで、昭和32年(1957)に高崎市本町にオープンしました。
六年後には道路拡張により鞘町に移転しましたが、25年という店の歴史の中で、人々が集い高崎の文化を語り、そして新しい文化を創造してきました。
その頃、高崎では音楽センター建設に向けて、市民による大規模な募金運動が始まっていました。店内に募金箱を置いて積極的に支援活動をした崔さんは、その運動を通して群響のマネージャーの丸山勝広さんをはじめ群響メンバーと親しくなりました。群響のメンバーに店で聴かせるクラシックレコードを選んでもらい、そして演奏もしてもらう。その代りコーヒーは二割引から無料でした。
コーヒーの香りと音楽、詩があふれた店内
昭和34年(1959)に第一回目が開かれた「生の音楽の夕べ」は、260回続きました。弦楽四重奏や管楽器合奏、ピアノ独奏、ソプラノやバリトン独唱、さらにギターや箏奏が行われました。
また1961年からは「詩の朗読の夕べ」が始まり、104回にも及びました。金子光晴、谷川俊太郎、茨木のりこ、吉原幸子など多くの詩人たちが訪れました。
コーヒー一杯で生のクラシック演奏や名だたる詩人の肉声が聞けるということで、愛好家はもちろん、それほど音楽や詩が好きでない人も、その文化的雰囲気を味わいに訪れました。
「あすなろ」の精神は引き継がれて
昭和57年(1982)、「あすなろ」は静かにその四半世紀の幕を閉じました。その年の秋、上越新幹線が開通。また翌年の群馬国体を控え、高崎市内は空前のホテルブームに沸いていました。
「あすなろ」の伝票の裏には「日本のウィーン高崎 高崎の夢あすなろ」「郷土を美しい詩と音楽で埋めましょう」とありました。その夢は、いま高崎がめざしている"音楽のある街"づくりに確かに受け継がれています。
コーヒー・カレー専門店高崎レストハウス
広がる空と山と川を望む最高のロケーション
 高崎レストハウス(テラス)
高崎レストハウス(テラス)
国道17号沿いの烏川に架かる和田橋のすぐ側、烏川と碓氷川が合流する辺りに、かつて緑の樹木が茂ったちょっと小高い丘があり、そこに高崎で初めてのカレー専門店「高崎レストハウス」がありました。焦げ茶色に塗られた木と白壁だけのシンプルな造りで、川に面した西側と北側は一面のガラス戸。外のテラスのテーブルに座ると、目の前には烏川と碓氷川が合流する豊かな水の流れと、観音山丘陵、霧積山、浅間山、そして右には榛名山の山並が広がっていました。
芸術・文化を愛好する人たちのサロン
「高崎レストハウス」が開店したのは、昭和34年(1959)。高崎製紙の社長だった黒崎義平さんが、東京から避暑で軽井沢に行く途中、休むところがほしいと考えたのが開店の理由でした。
昭和39年(1964)から、マネージャーになった木暮久子さんの人柄、自らも画家であったその人脈もあって、多くの文化人が立ち寄るようになりました。高崎周辺の文学サークル、演劇や絵画などのグループが会議などに使いました。群馬漫画同人、群馬詩人会議、高崎映画祭の前身である観たい映画を観る会、画家やデザイナーなど。ときには、絵画など様々な作品が飾られました。
「お客様にも従業員にとっても、満足のいく店であるにはどうしたらいいかを、常に考えて行動しました」と、木暮さんは当時を振り返る。
味にこだわり著名人も多く立ち寄った店
当時有名人もよく訪れました。政治家の藤山愛一郎、作家では遠藤周作、野坂昭如、羽仁五郎など、また美術評論家として知られる洲之内徹がふらっと訪れ、川の見える窓際の席で何時間も座っている姿もありました。
演劇鑑賞会の後には出演していた俳優の懇親会にも利用され、西村晃、西田敏行、高橋悦治、太地喜和子や、歌舞伎の尾上松禄一座、前進座の座員など、多くの俳優が訪れました。
また、レストハウスのカレーは、英国風と印度風の二種類あり、印度風カレーにはヨーグルトが付いて、当時の高崎には珍しいものでした。本格的な味を提供するため、木暮さんも料理人も、評判のホテルや店に足を運んでは、美味しいものを研究したということです。
時代の要請に応えて
レストハウスの閉店は突然でした。昭和63年(1988)、木暮さんが長年の念願だった絵の勉強でパリに留学するために辞め、その後二年ほどは別の人が経営していました。しかし木暮さんがいなくなると、店の雰囲気が変わり、常連客が姿を見せなくなって、平成2年(1990)に閉店しました。
「時代に必要とされ、輝くことのできた幸せな店でした」。留学し激変するヨーロッパを目の当たりにし、今も版画など創作活動に取り組む木暮さん。変化は世の常であり、普遍的な真理を求めて自身も常に変わりたいという思いは「高崎レストハウス」についても例外ではないようです。