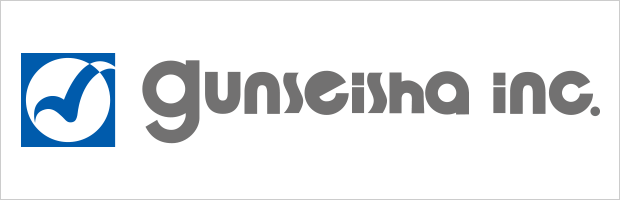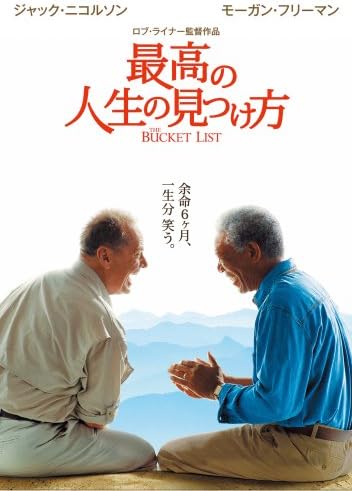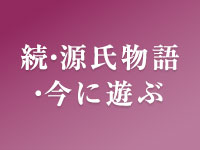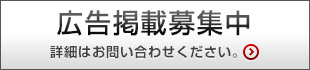続・源氏物語・今に遊ぶ
巻1桐壺 ②
吉永哲郎
前回、「男の涙」を少々書きましたが、「泣く」という行為には、様々 な人間の感情を示すと同時に、単純に涙を流す行為が悲しさやうれしさを表すだけでなく、「泣く」という人間の姿に、民族によって、時代背景によって、意味が違います。特に男性と女性とでは、その姿の受け止め方が違います。
私的な場、公的な場とでは、宗教的・政治的な背景によって違います。今はあまり耳にしませんが、「男の子だろう」といって、なかなか泣き止まない子に向かって声を掛ける周りの人がいました。ならば女性は 「めそめそするのをよし」とするのか、と。
明治の日本近代化を象徴する「富国強兵」の言葉には、人間のありのままの姿を規制することが多々ありました。特に太平洋戦争中に於ける政府や軍部の揚げるスローガンには、非人間的行為を容認強調することばが多く聞かれました。
こうした時代背景下では、「源氏物語」は否定され、国の防衛の先端にあたった万葉人の防人の歌が、注目されました。阿川弘之の小説『雲の墓標』に、この翻弄された「古典」の文庫本を、鉢巻の額にあて操縦かんを握り、死へ赴く学徒兵の姿が描かれています。こうした意味を含め、忘れてはならない人間の涙の姿が、桐壼の巻に描かれていると思います。