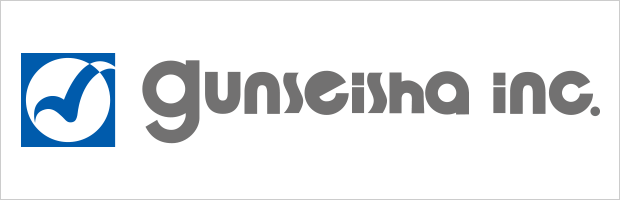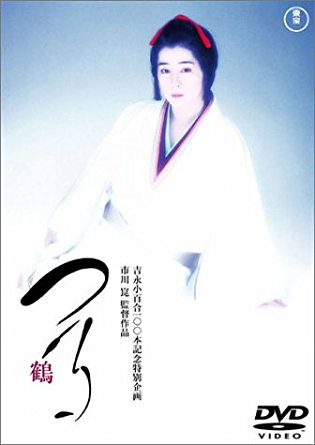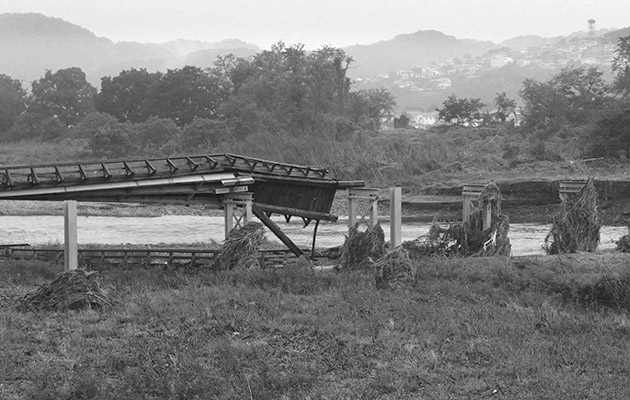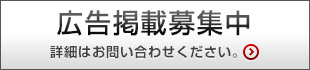続・源氏物語・今に遊ぶ
巻1・③
吉永哲郎
「男の子だから泣くんじゃないよ」という、ことばは今はあまり聞きませんが、「男の涙」が一つの文化現象として、特に明治以後の日本近代では扱われてきました。私は「涙」は、人間の感情表現の激しい姿だと考えています。涙の場面は、その前後を通して課題としてきた事柄の解決への手がかりで、重要な感情の凝縮された姿です。
言葉にならないその時の、その場面での、内に秘めた感情が吐露した、生き物としての人間の姿です。源氏物語が否定された時代は、人間否定の状況を意味していると思います。
こうしたことを念頭において源氏物語を読みますと、桐壺の巻で、死を直前にした愛する桐壺の更衣(あるかなきかに消え入りつつものしたまふなる)を、宮中から送り出すことをためらう帝を、帝(オカミ・上・神)という絶対的存在としてでなく、一人の人間として、さらに別れの悲しみの極限に達した時、「よろづのことを、泣く泣くのたまはす」と、描かれています。人間らしい涙や泣くという行為を描くことによって、人間らしい豊かな感情と心理の奥底を表現しているところに、紫式部のたぐいまれなる筆力を感じます。
さて、帝の桐壺の更衣への愛の姿は、当時の人々にどのように受け止められていたでしょうか。以下次号で。
- [前回:巻1桐壺 ②]